生活保護法は、第1条から第10条までに「この法律の本質的なこと」がほぼ全て表われている。
なので、第1条から第10条までを書いていく。
では、第1条から。(マーカーは筆者)
○生活保護法 (昭和二十五年五月四日 法律第百四十四号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
この第1条は、先ず二つの大きな意味がある。
一つには、星の数ほどある我が国の法律の中でも極めて稀有な「憲法に由来した法律」であることを明記している点である。この法律と憲法との関係を更に知りたい方は、「朝日訴訟」、「プログラム規定説」を調べていただきたい。
もう一つには、理念規定であることが多い種々の法律の第1条と違い、生保法第1条は「極めて実働的である」という点。「この法律が行うべきこと」が端的に明記されている。すなわち、①「最低生活の保障」と②「自立の助長」である。このように、第1条は「理念」ではなく「実働性」に満ちている。第2条以降は、「①と②の具体的な実施方法」が規定されていると考えればよい。
さらに細かく条文を読み解いてみる。
「国が」と明記していることで生活保護が「国家責任」で行われることを明らかにしている。
また、「すべての国民に対し」という表記からは、この法律による保護の対象となるのは「日本国民のみ」であることも分かる。(※いわゆる「外国人保護」は「人道的見地から生活保護制度を準用した予算措置上のもの」である。そのため、行政不服審査法による審査請求はできない。「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号各 都道府県知事あて厚生省社会局長通知)参照。)
また、「すべて」という表記は、第2条とも深く関わる「欠格条項は無い」という表明でもある。
「困窮の程度に応じ、必要な保護を」行うとは、この法律による保護が定型(額)的・一律型の給付ではなく、それぞれの「世帯」(※後述)の困窮の内容に応じて保護の内容も変わることを端的に表している。
そうした保護を適用することにより、「最低限度の生活」を保障しつつ「自立を助長」する、という建付けである。
第1条だけみても、短い条文にこれだけの意味が込められているのである。
第2条は第4条と関連するので、次回はその2つの条文について書いてみたい。
そういえば、愛犬はなさん🐕のこと、書いていないなあ…
生活保護法について書いてみた(その1)
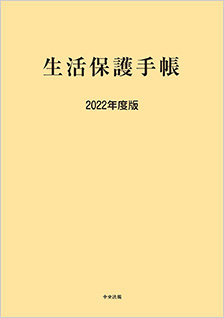 生活保護のこと
生活保護のこと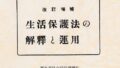
コメント